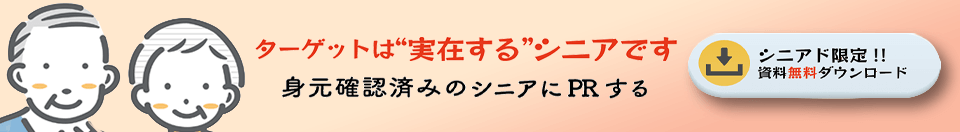シニアの終活と葬儀への意識変化を踏まえたマーケティング戦略のポイント
近年、シニア層の終活や葬儀に対する意識は大きく変化しています。葬儀や終活関連企業にとって、これらの変化を理解し、適切な戦略を立てることが重要です。
本記事では、シニア層の終活や葬儀に関する意識の変化、選ばれる葬儀の形態、そして効果的なマーケティングアプローチについて考察します。
目次
- シニアの終活と葬儀に関する意識の変化
- 終活の一環として見直される「葬儀の選択」
- シニアの終活と葬儀に向き合うためのアプローチ
- マーケティング戦略として重要なポイント
- まとめ:シニアの声を活かしたマーケティングが重要
1.シニアの終活と葬儀に関する意識の変化
近年、シニア層の終活への関心が高まる一方で、具体的な準備や葬儀の選択に悩む人も増えています。ここでは、シニアの終活・葬儀に関する意識の変化と、終活を始める年代やその内容についてを解説します。
終活の認知度と取り組み状況
シニア層の終活に対する意識は年々高まっており、多くの人がその重要性を認識しています。
ハルメクホールディングスが実施した「50〜79歳男女に聞いた終活に関する意識調査」によると、終活に取り組んでいる人や、必要性を感じている人の割合は2021年、2023年どちらの調査でも70%を越え、変わらず高い水準を維持しています。これは、健康や寿命に対する意識の変化、家族への負担軽減の考えが根付いていることが背景にあると考えられます。
また、終活への関心は年代が上がるにつれて高まる傾向があり、特に70代では「すでに終活を始めている」と回答する人の割合が顕著に増加しています。一方で、50代以下では「興味はあるが、まだ始めていない」という回答も一定数あり、終活を意識しながらも具体的な行動には移せていない人が多いことが分かります。そのため、終活に関する情報提供や具体的な進め方の提示が、今後ますます求められるでしょう。
終活を始める年代と内容
終活を始める適切なタイミングについては、個人のライフステージや健康状態によって異なりますが、シニアライフ総研の調査では、40~50代の人は「50代のうちに終活を始めるべき」と考える人が22.8%に上ることが明らかになっています。
一方で、実際に終活を始めるのは60代以降が56.3%と一番多くなりますが、「まだ始めていない」という人は43.8%となり少なくありません。
また、終活の具体的な取り組みとしては、「資産整理」に関心を持つ人が47.7%と最も多くなっています。特に60代以上では、遺言書の作成やお墓の準備、葬儀の計画といった、より具体的な取り組みに関心を示す傾向が強まることが分かりました。
終活をスムーズに進めるためには、早い段階から情報収集を行い、自分に合った方法を検討しておくことが重要です。最近では、終活に関するセミナーや相談会、オンラインでの情報提供も充実しており、気軽に学べる環境が整いつつあります。
参考:50~79歳男女に聞いた「終活に関する意識調査」 ハルメクホールディングス
2.終活の一環として見直される「葬儀の選択」
シニアの終活意識が高まる中、葬儀の選び方にも変化が見られます。家族葬や直葬など小規模な葬儀を希望する人が増えており、費用や家族への負担を考慮する傾向が強まっています。ここでは、その実態を探ります。
葬儀の形態の多様化
近年、葬儀の形態は多様化しており、家族葬や火葬式(直葬)を選ぶ人が増加しています。ハルメクホールディングスの調査によると、50〜79歳の男女のうち半数以上が家族葬を希望していることが分かります。家族葬は近親者のみで葬儀が執り行われ、参列者の負担が少なく、比較的低コストで済むのが特徴です。
また、コロナ禍を経て、葬儀のあり方はさらに変化しました。感染対策の影響で大規模な葬儀を避ける動きが強まり、家族葬や火葬式の割合が増加しています。特に火葬式は、費用を抑えつつシンプルに故人を見送れる方法として注目されています。
こうした変化の背景には、「家族に負担をかけたくない」「形式よりも心のこもった送り方をしたい」というシニア層の意識の変化があると言えるでしょう。一方で、故人との最後の別れを大切にしたいと考える家族との間で意見の違いが生じることもあり、葬儀の形態選びには慎重な判断が求められています。
葬儀費用の推移
葬儀費用は2015年以降大きな変化はありませんでしたが、2022年の調査では、コロナ禍の影響で葬儀の規模縮小が進み、費用にも変化が見られました。
2013年の葬儀費用の平均は202.9万円でしたが、2022年で110.7万円まで大幅に下がっています。家族葬や火葬式(直葬)の普及により、費用を抑える傾向が強まっていったと言えるでしょう。特に火葬式は葬儀の中でも低コストで、2020年から2022年で利用者が6.5%増加し、葬儀を選ぶ全体の1割以上を占める結果となりました。
また、参列者数の減少も費用変化の要因です。2013年では平均78人の参列でしたが、2024年には平均38人まで減少し、式場や祭壇の規模も縮小。結果として葬儀全体の費用が抑えられています。
さらに、葬儀社のサービスの選択肢が増え、従来のパッケージ型に加えて、必要なサービスだけを選べるプランも登場。ニーズに応じた柔軟な価格設定が可能になりました。今後も少子高齢化や核家族化の進行により、家族葬や直葬の割合が増えると予想されます。
参考:お葬式に関する全国調査からみる葬儀費用の推移・変化(2013年~2024年) いい葬式
3.シニアの終活と葬儀に向き合うためのアプローチ
シニア層の終活や葬儀に対する意識は変化しており、本人と家族の双方に適切なアプローチが求められます。シニア本人は、エンディングノートの作成や資産整理、葬儀の事前相談などを進める傾向が強まっています。一方、家族は本人の意向を尊重しつつも、突然の対応に備えたいと考えています。
しかし、葬儀の形態については両者の考えが異なることも多いです。シニアは負担をかけたくないと火葬式(直葬)や家族葬を希望する傾向がある一方、家族は「しっかり送りたい」と考える場合もあります。このギャップを埋めるために、正しい知識を提供し、納得のいく選択ができるよう支援することが重要です。
4.マーケティング戦略として重要なポイント
終活や葬儀に関するサービスを提供する企業にとって、効果的なマーケティング戦略を立てることは重要な課題です。シニア層とその家族に対して、安心感を与え、信頼を築くためには、適切な情報提供や相談体制の充実が欠かせません。
そこで、マーケティング戦略として重要なポイントを解説します。
情報提供の充実
終活や葬儀に関する具体的な情報を提供し、シニア本人と家族が適切な選択を行えるよう支援することが大切です。
例えば、終活の進め方、葬儀の種類や費用の相場、事前に準備すべきことなどを分かりやすくまとめたガイドブックやウェブコンテンツを提供することで、必要な情報を得やすくなります。
また、動画やSNSを活用した情報発信も、より多くの人にアプローチできる有効な手段です。
相談窓口の設置
終活や葬儀に関する悩みや疑問を気軽に相談できる窓口を設けることで、シニア層やその家族の不安を解消できるでしょう。対面相談、電話相談、メール、チャット対応など、多様な方法を用意することで、幅広い層に対応可能になります。
また、事前相談サービスを充実させることで、いざという時に慌てずに済む環境を整えることができます。
オンラインとオフラインの融合
総務省が発表している2023年のインターネット利用率は、50〜59歳で97.2%、60〜69歳で90.2%と高く、シニア層のITリテラシーの向上から、オンラインでの情報収集や相談を活用する人も増えていると言えます。
そのため、ウェブサイトやSNSを通じた情報提供、オンラインセミナーの開催など、デジタルを活用したアプローチを強化することが有効です。
一方で、すべてのシニアがデジタルに慣れているわけではないため、従来の対面相談会やパンフレットの配布、地域のコミュニティでの説明会といったオフライン施策も継続し、幅広いニーズに対応する必要があります。
シニア向け広告についての特徴はこちらでご紹介していますので、ご確認ください。
5.まとめ:シニアの声を活かしたマーケティングが重要
シニア層の終活における葬儀の検討意識は変化しており、企業はその動向を正しく把握し、適切なアプローチを行うことが求められます。そのためには、シニア層がどのような情報を求め、どのように終活を進めているのかを理解することが重要です。
近年では、シニアのインターネット利用率上昇に伴い、シニア向けのオンラインコミュニティも広がりを見せています。こうした場では終活に関する情報交換が活発に行われています。たとえば、シニア専用SNS「おしるこ」は、シニア同士が終活全般について気軽に意見を交わしたり、情報収集などができる場です。企業にとっても、シニアの意識の変化を把握し、マーケティングの参考にする手がかりのひとつとなる可能性があります。
シニア層の具体的なニーズを理解することで、より的確なマーケティング施策を打ち出すことが可能になります。データに基づいた戦略と柔軟な対応が、シニア層のニーズに応えるカギとなるでしょう。
「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。
「シニアド」へのご相談を1クリックで予約しませんか?
シニア市場への理解を深め、効果的なアプローチをサポートいたします。マーケティング戦略、ブランディング強化など、ご検討中の課題をぜひお聞かせください。 専門スタッフが丁寧に対応いたします。