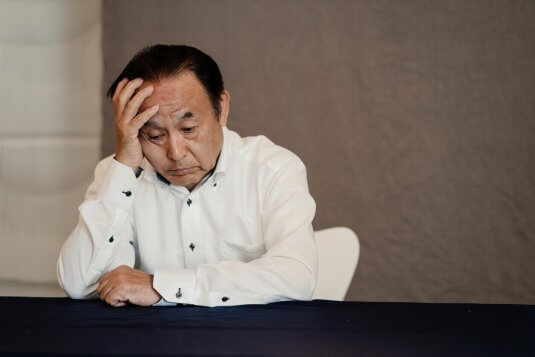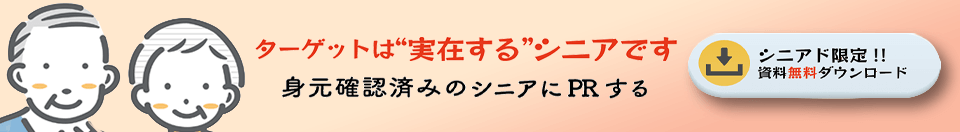新人類世代はサブカルチャー好き?新人類世代が生きた時代とサブカルチャーとの関係を紹介
一般的に、アニメや漫画、ゲームやアイドルなどといった、オタク文化とも呼ばれる「サブカルチャー」は、ある程度若い世代向けの文化だと思われがちです。しかし、1960年前後に生まれた「新人類世代」は、実はサブカルチャーが日常生活に定着し始めた時代を経験しており、サブカルチャーに対する受容性が高いのです。新人類世代が生きてきた時代を知って、新人類世代に対する効果的なマーケティング戦略を考えることにつなげていきましょう。
目次
- 新人類世代とは?
- 新人類世代は趣味への支出を惜しまない?
- 新人類世代はサブカルチャーが日常にあふれだした最初の世代
- 新人類世代はインターネットに対しても受容的
- 新人類世代に効果的なマーケティング戦略を考えよう
1.新人類世代とは?
団塊世代、Z世代などといったように、人々は生まれた時期やその社会背景によって分類されることがあります。生まれた時期が近い人々は、同じような時代や社会背景を生きてきたことから、似通った特徴や思考、行動の傾向があると考えられているためです。
今回取り上げる「新人類世代」は、1955年から1967年頃に生まれた世代で、年齢で言えば2025年に58歳から70歳になる世代を指します。有名人で言えば、秋元康さん、尾崎豊さん、とんねるず、岩崎良美さん、清原和博さんなど(当然ながらほかにも多数)が該当します。また、2019年に即位した現在の天皇陛下も1960年生まれなので、生年だけでいえば新人類世代ということになります。
新人類世代のほかにも、さまざまな世代の呼び方があります。生まれた順に並べると下記の表の通りです。中には、生まれた時期がかぶっている世代もあります。また、下記の分類はあくまで一例であり、厳密な定義はありません。
| 世代 | 生まれた年 |
|---|---|
| 団塊世代 | 1947年~1949年頃 |
| しらけ世代 | 1950年~1965年頃 |
| 新人類世代 | 1955年~1967年頃 |
| バブル世代 | 1965年~1970年頃 |
| 団塊ジュニア世代 | 1971年~1974年頃 |
| ミレニアル世代 | 1980年~1995年頃 |
| さとり世代 | 1985年~1995年頃 |
| ゆとり世代 | 1987年~2004年頃 |
| Z世代 | 1995年~2010年頃 |
世代ごとの特徴の詳細については、下記の記事を参照してください。
2.新人類世代は趣味への支出を惜しまない?
新人類世代、言い換えると1960年頃に生まれた世代の消費活動に関する特徴の1つが、趣味への支出を惜しまないことです。
少し古いデータですが、2019年度に内閣府が実施した「高齢者の経済生活に関する調査」という調査結果があります。この調査では「今後、優先的に使いたい支出項目(複数回答)」という質問項目に対して、60歳〜64歳の男女の55.4%が「趣味やレジャーの費用」と回答しています。この数字は、ほかのどの支出項目よりも高く、これより上の世代よりも高い数字でした。2019年度の時点で60歳〜64歳ということは、1955年度〜1959年度に生まれたことになりますから、この結果は概ね、新人類世代は趣味への支出を惜しまないという傾向を示していると言えます。
参考:高齢者の経済生活に関する調査 Q12:今後優先的に使いたい支出項目(内閣府)
一般的にシニアには、所得がない中で貯金を崩しながら、支出を絞って生きていくというイメージがあります。しかし新人類世代はそれよりも上の世代のシニアと違い、自身の資産を運用しながら、あるいは働いて所得を得ながら、自分のためにお金を使っていく傾向があると分析されています。
また、新人類世代は、高度経済成長期のまっただ中で育ち、若年期にはバブル景気を謳歌しました。上の世代と比べて、豊かな時代を生きてきて、ライフスタイルが全く異なるのです。こういった新人類世代の特徴が、趣味への支出を惜しまない傾向につながっていると考えられます。
3.新人類世代はサブカルチャーが日常にあふれだした最初の世代

新人類世代のもう1つの特徴は、エンターテイメントやサブカルチャーが、日常にあふれだした時代を生きてきたことです。なお、サブカルチャーとは、ある文化の主流ではなく、独自の性質を持つ独立した文化のことを指します。日本では、漫画やアニメ、ゲームやアイドルなどに関連する文化、いわゆるオタク文化を指すことが一般的です。
参考:サブカルチャーとは? 意味や具体例、日本の代表的サブカルチャーをわかりやすく解説 | マイナビニュース
日本でテレビ―のカラー放送が始まったのは1960年で、まさに新人類世代が生まれた時期です。1963年には、日本初のロボットアニメおよび30分アニメとされる『鉄腕アトム』が放送を開始します。1970年代には『ドカベン』『BLACK JACK』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『ガラスの仮面』『キン肉マン』といった、現在でも知名度の高い漫画の連載が始まっているのです。
また、1978年に稼働を開始したアーケードゲームの『スペースインベーダー』は空前の大ヒットとなりました。
1970年代にはアイドル文化もまた花開きます。山口百恵さん、キャンディーズ、ピンク・レディー、榊原郁恵さんといった、そうそうたる顔ぶれのアイドルがデビューしたのがこの時代です。
その一方で当時の社会では、安保闘争の敗北や、あさま山荘事件といった重大事件の勃発を経て、学生の政治運動の失敗が決定的になり、その後の世代の若者は、政治から距離を置くようになります。政治に無関心な若者となった最初の世代もまた、新人類世代でした。このこともまた、上の世代と大きく異なる新人類世代のライフスタイルの形成に一役買ったのです。
1980年代に入ってもサブカルチャーはさらに発展していきます。1983年のファミリーコンピュータの発売、そして1985年の、ファミリーコンピュータ対応ソフトである『スーパーマリオブラザーズ』の発売などはその典型と言えるでしょう。「オタク」や「新人類」という言葉が実際に生まれたのもこの時期です。「従来とは異なった感性や価値観、行動規範を持っている」という意味合いで、当時の若者を新人類と称したのです。1986年には「新人類」が新語・流行語大賞に選出されました。
そしてご存知のように、1980年代後半から1990年代初頭に、日本は空前の好景気、いわゆるバブル景気を迎えます。サブカルチャーが花開き、景気がよかった時代を学生や若手・中堅会社員などとして過ごしたことによって、趣味への支出を惜しまない新人類世代の消費活動の傾向は、決定づけられたと考えられます。
4.新人類世代はインターネットに対しても受容的
シニアという言葉からは、インターネットに疎い、デジタル機器に弱いといったイメージを抱きがちです。しかし、新人類世代はインターネットをそれなりに使いこなしています。2023年度に総務省が実施した調査によると、50代の97.5%、60代の93.7%は、スマートフォンを利用しています。また、50代の87.8%、60代の72.7%が動画共有・配信サービスの『YouTube』を利用していることも明らかになっています。いずれも、若い世代に比べれば低い数字ではありますが、インターネットの広告は、新人類世代にも十分に「見てもらえる」のです。
また、ソーシャルメディア系サービス(SNS)の利用率も低くはなく、特に『LINE』は50代〜60代のほぼ90%が利用しています。新人類世代の間でのSNSを通じた情報拡散も、十分に期待できるのです。
参考:令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 <概要>(総務省)
5.新人類世代に効果的なマーケティング戦略を考えよう
サブカルチャーはある程度若い人向けの文化だと捉えられがちですが、新人類世代が育った時代には、既に日常に根付いた文化です。また、新人類世代は経済的に豊かな時代を生きてきたことから、趣味への支出を惜しまない傾向があり、人によってはその支出の対象が、サブカルチャー関連の好きな作品ということもあるでしょう。したがって、例えばサブカルチャーとタイアップした広告には、新人類世代に対する一定の訴求効果が期待できます。また、新人類世代はパソコンやスマホといったデジタルデバイスに比較的慣れており、動画サイトやSNSなどを通じた訴求も、上の世代と比べると容易です。新人類世代への効果的なマーケティング戦略については、以下の記事もご参照ください。
なお、新人類世代を対象にマーケティングを検討している方には、50歳以上限定のSNSである『おしるこ』をおすすめします。おしるこに広告を掲載することで、新人類世代を含めたシニアに対して効率的なPRが可能なだけでなく、会員の日記や、SNS内でのグループのやりとりなどから、シニアのニーズや潜在的な欲求をくみ取れます。また、おしるこでの記事広告をきっかけに商品を購入したユーザーが、使用した体験をおしるこの日記や動画で共有し、他のユーザーの購入につながることも期待できます。
「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。
「シニアド」へのご相談を1クリックで予約しませんか?
シニア市場への理解を深め、効果的なアプローチをサポートいたします。マーケティング戦略、ブランディング強化など、ご検討中の課題をぜひお聞かせください。 専門スタッフが丁寧に対応いたします。
 お問い合わせ
お問い合わせ