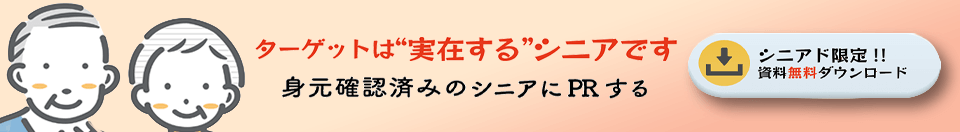シニア向けアンケートの集計方法は?エクセルの活用方法もあわせて解説
シニア向けアンケートを行う場合、設問作成だけでなく、集計方法に苦労する方も多いでしょう。せっかくアンケート調査をしたのに、集計や分析の方法が分からず、活用できないまま終わってしまうケースは多くあります。
本記事では、シニア向けアンケートの集計方法を詳しく解説します。エクセルを活用した集計方法や、自社でアンケート調査をする課題点についても解説しますので、これからマーケティングリサーチを実施しようと考えてる方はぜひ参考にしてください。
目次
1.シニアへのアンケート調査の重要性
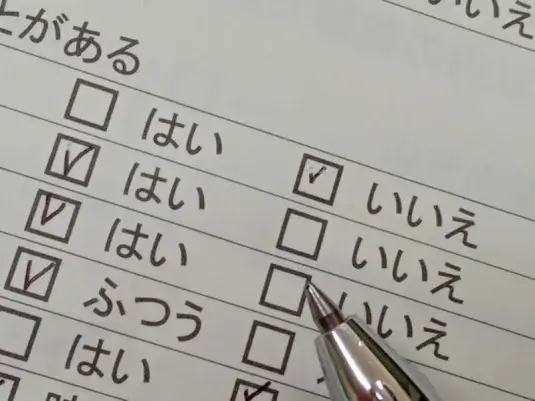
「シニアの傾向はわかっているし、アンケート調査をする必要性をいまいち感じない」という方も少なくありません。しかし、現在のシニア層はライフスタイルや価値観が変化してきており、最新のインサイトを知らないと、正しいマーケティングができなくなっています。
それでは、シニア層がどのように変化してきているのかについて、以下で解説します。
年代毎の違い
ひとくちに「シニア」といっても、年代や状態によって趣味趣向やライフスタイル、消費行動の傾向などは大きく異なります。
シニア層の主な分類
- アクティブシニア:アクティブに行動する方
- ディフェンシブシニア:活動意欲はあるが消費行動は消極的な方
- ギャップシニア:健康状態に不安のある方
- ケアシニア:介護が必要な方
例えば、同じ80歳の方でも、アクティブシニアからケアシニアまで幅広く存在するのです。また、同じディフェンシブシニアであっても、70歳の方もいれば、90歳の方もいます。
シニアというのは非常に大きな括りなので、まずどんな年代が該当するのか、年代ごとの特徴や流行は何か、またどんな状態の人々が存在するかを細かく把握する必要があります。
価値観の変化
時代とともに、シニア層の価値観も大きく変化しています。少子高齢化や核家族化、年金不安の増大などによって、消費行動にもさまざまな変化が生じているのです。
また、平成30年頃と比べて、友人のいない方が増加しており、孤独を感じる人が増えているといった変化もあります。コロナ禍や、地域住民との関わり方の変化などが影響していると考えられるでしょう。
こうした変化を通じて、シニア層がどのような商品・サービスに興味を持っているか、生活や人付き合いにおいて何を重視するかについても、さまざまな変化が生じていると考えられるでしょう。
ライフスタイルの変化
シニアのライフスタイルにも、大きな変化が見られます。特に大きな変化は、デジタルデバイスの普及です。
内閣府の調査によると、65歳以上で23.7%、65〜74歳では44.2%の人が『インターネットで情報を集めたり、ショッピングをする』と回答しています。
こうしたデジタルデバイスの普及によって、日々の情報収集や買い物などの仕方が、大きく変わっているのです。
また、前述したように「アクティブシニア」「ケアシニア」といった、それぞれの状態によっても、ライフスタイルは変化しています。
健康寿命が延びて、多種多様なライフスタイルが実現できる時代になったからこそ、シニア層への詳細なリサーチが求められるのです。
2.アンケート集計に活用できるツール
シニアのアンケート集計に活用できるツールには、以下のものがあります。
アンケート集計に活用できるツール
- Googleフォーム
- Microsoft Forms
- Excel・Googleスプレッドシート
シニアへのアンケート集計をする際は、使いやすさが非常に重要です。今回は、上記の代表的ツールについて、それぞれの特徴を解説します。
Googleフォーム
Googleフォームは、誰でも簡単にアンケートの作成・集計・分析ができるツールです。利用者が多いため、ネット検索をすれば詳しい使い方についてすぐ調べられる点がメリットです。
また、Googleスプレッドシート用に集計データを出力できるのもメリットです。同じGoogleのツールなので、連携機能が充実しており、スプレッドシートで集計や分析をしたい方にもぴったりのツールとなっています。
ほかにも、最大10GBのファイルを共有できたり、Google Apps Scriptを活用して拡張機能プログラムを自作・実装できたりと、利便性の高いツールです。
Microsoft Forms
Microsoft Formsは、Microsoft Office(365)やWindowsで有名なMicrosoftのアンケートツールです。集計フォームの作成から集計、分析までを一貫して行えます。
Microsoft Formsの特徴は、アンケートフォームの作りやすさです。ワンクリックで簡単に新規作成でき、豊富なテンプレートからデザインを探せるので、専門知識がなくても理想的なアンケートフォームを作れるでしょう。
また、OneDriveにある素材を活用できるのもメリットです。Microsoft365を使用している方は、仕事で使うファイルをOneDriveに保存してあるでしょう。このドライブ内の素材をそのままアンケートに活用できるので、より手間をかけずにアンケート作成ができます。
Excel・Googleスプレッドシート
GoogleやMicrosoft以外のアンケートツールを使用している方でも、集計はExcelやGoogleスプレッドシート等の表計算ソフトを使用しているケースが多くあります。
表計算ソフトを使用するメリットは、自由度が高い点です。さまざまな関数を使えるので、自分にあった手法で集計・分析ができます。
また、グラフ化しやすい点も魅力です。表計算ソフトでは、ワンクリックでデータをグラフ化できます。データに応じて、棒グラフ・円グラフ・折れ線グラフなどを使い分けられて、デザインも変更できるため、プレゼン資料を作成する際も便利です。
GoogleフォームやMicrosoft Formsでも分析・集計は可能ですが、より高度な作業をしたい時や、デザインにこだわってグラフを作成したい時は、表計算ソフトを使用すると良いでしょう。
3.シニアのアンケート集計・まとめ方のポイント
アンケート集計の手法には、さまざまな種類があります。
アンケート手法の種類
- 単純集計
- クロス集計
- 自由記述集計
代表的な3つの手法を知って、知りたい情報にあわせた集計をしていきましょう。
単純集計
単純集計は、回答内容をただまとめる方法です。アンケート集計方法としては最もシンプルで、多くの方がやったことのある方法でしょう。以下で、単純集計の結果をまとめた表(単純集計表、GT表)を紹介します。
WebサービスAを利用してみた感想はいかがでしたか?(n=10)
| 回答者 | 満足 | 普通 | 不満 |
| A(20代) | 〇 | ||
| B(30代) | 〇 | ||
| C(20代) | 〇 | ||
| D(20代) | 〇 | ||
| E(30代) | 〇 | ||
| F(40代) | 〇 | ||
| G(40代) | 〇 | ||
| H(30代) | 〇 | ||
| I(20代) | 〇 | ||
| J(30代) | 〇 | ||
| 人数 | 4人 | 4人 | 2人 |
| 割合 | 40% | 40% | 20% |
単純集計は、アンケート結果をおおまかに把握するのに適しています。
クロス集計
クロス集計とは、単純集計の結果に、年齢や性別といった回答者属性を掛け合わせて(クロスして)集計する方法です。
WebサービスAを利用してみた感想はいかがでしたか?(n=10)
| 回答者 | 満足 | 普通 | 不満 |
| 20代 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 30代 | 2人 | 2人 | 0人 |
| 40代 | 2人 | 0人 | 0人 |
上記のようにクロス集計すると、年齢や性別ごとの傾向を掴めます。今回であれば「年齢層が高いほうが、満足度も高い」と分かるでしょう。
クロス集計を行うと、例えば「若年層が不満を感じている原因は?」「30代以降の人々に対する集客施策は?」など、具体的な課題や解決策を考えるのに役立ちます。
自由記述集計
自由記述集計は、文章や単語、数字の回答に用いる集計方法です。まずは、自由記述回答の例を見てみましょう。
自由記述回答の例
- 子ども時代のおこづかいは?:3,000円、6,000円など
- 学生時代やりたかった仕事は?:花屋、消防士、パティシエなど
- 新卒時代に感じたギャップは?:裁量が大きい、手取りが少ないなど
長方形で「自由にお書きください」などと書かれている回答欄をイメージすると、分かりやすいでしょう。こうした自由記述は、回答者ごとに内容がまったく異なるため、専門的な集計が求められます。
上記のように、自由記述集計の代表的な手法として「アフターコーディング」と「テキストマイニング」という2種類があります。
アフターコーディング
アフターコーディングでは、まず類似回答をまとめて選択肢化し、選択肢ごとに単純集計やクロス集計を行っていきます。例えば「新卒時代に感じたギャップ」であれば、給料・人間関係・働き方・雰囲気などに各回答を分類して、集計するといったかたちです。
テキストマイニング
テキストマイニングとは、回答文章を単語ごとに区切り、各単語の出現率や、相関関係などを集計する方法です。テキストマイニングを人力で行うのは非常に手間がかかるため、集計ツールを使用するのが一般的となっています。
主な分析手法
アンケート結果をただ集計するだけでは、データを活用できません。集計データを分析して、何が読み取れるかを分析してはじめて意味があるのです。
それでは、代表的な分析手法を紹介しましょう。
アンケート結果の主な分析手法
- 時系列分析:アンケート結果を時系列で比較する方法
- クラスター分析:縦軸と横軸を設定して各回答を配置する分析方法
- アソシエーション分析:仮定を立てたうえでデータの相関関係を探る手法
- 主成分分析:複数の変数データを「大一主成分」「第二主成分」と分類して分析する方法
- 決定木分析:目的変数(購入率、返信率など任意設定)を、さまざまな説明変数(年齢、性別など任意設定)でクロス集計して分析する方法。
- センチメント分析:一般的に、さまざまな要素の大して肯定的・中立・否定的の3段階で評価し分析する方法。主にテキストマイニングにおいて用いる。
- 出現頻度分析:特定の単語がどれくらい出現するかの頻度を出す分析方法
どういった調査結果を扱うか、データを何に活用したいかによって、適切な分析方法を用いる必要があります。
4.エクセル(Excel)でアンケート集計を行う方法
アンケート集計を行う場合、多くの人が使用するのがエクセル(Excel)をはじめとした表計算ソフトです。昨今では、Googleスプレッドシートを使用する方も多いかもしれません。
エクセルを使用してアンケート集計を行う場合、以下のような関数を使用するのが一般的でしょう。
エクセルでアンケート集計する際によく使う関数
- COUNTIF:条件を満たすセルが何個あるか
- COUNTIFS:いくつかの条件を満たすセルがいくつあるか
- SUMIF:条件に合うセル内の数値の合計
- SUMIFS:2つの条件を満たすセル内の数値の合計
- AVERAGEIF:条件を満たすセル内の数値の平均
- AVERAGEIFS:いくつかの条件を満たすセル内の数値の合計
例えば「満足と回答した人数」ならCOUNTIF(満足、と書かれたセルの合計)を使用します。この「満足と回答した男性の人数」ならCOUNTIFSを使用するでしょう。
今回紹介した以外にもさまざまな関数があるので、まずはどういった関数があるのかを知って、より効率よく集計・分析が行えるようにしましょう。
5.自社でアンケート調査を行う際の課題
自社でアンケート調査を行う場合、手間がかかる、外注すると費用がかさむといったデメリットがあります。課題点を把握したうえで、自社でアンケート調査をすべきか判断しましょう。
手間がかかる
自社でアンケート調査を行う場合、以下のような作業が発生します。
アンケート調査実施時の作業
- アンケート調査の目的や仮定の設定
- 設問の作成
- アンケートフォームや用紙の作成
- オフラインであれば、会場の手配や設営
- 回答者選定
- アンケート実施、集計
- データ分析
上記のようにたくさんの作業が発生し、1〜2か月はかかるのが一般的です。アンケート調査のノウハウがないと、設問作成だけでもかなりの時間と手間がかかるでしょう。
アンケートの専門知識が必要
設問の作成には、専門的な知識が必要です。設問や選択肢を適切に作成できないと、回答に偏りが出たり、欲しいデータが得られなかったりして、アンケートを実施した意味がなくなってしまいます。
よくあるのは、設問に否定疑問文を使用してしまうケースです。
「〜はおいしくないですか?」と否定+疑問の文章を使うと、「まずいですよね?」「おいしいですよね?」のどちらとも取れてしまいます。結果「はい=おいしくないです」「はい=おいしいです」と、同じ回答なのにどちらの意味か分からなくなってしまうのです。
また回答者の選定や、集計、分析に関しても、データを適切に扱うための知識が必要になります。アンケート調査の知識がないまま進めると、ただ時間と労力を無駄にしてしまいかねません。
外注すると費用がかさむ
時間をかけられない、知識がないといった場合には、アンケート調査を外注しようと考えるでしょう。しかし、アンケート調査を外注すると、かなりの費用がかかります。
サンプル数1,000人前後、設問数10問前後であれば、20万円ほどはかかります。サンプル数や設問数を増やす場合や、自由記述回答を入れる場合だと、さらに費用がかかるでしょう。
また、郵送調査やオフライン調査だと、印刷代や郵送費、会場費などもかかってきます。またアンケート調査の品質も会社によってバラつきがあるため、コストを回収できるほどの成果があるかも不透明です。
6.シニアのインサイトなら「おしるこ」
シニア向けアンケート調査をしたいとお考えの企業におすすめなのが、シニア向けSNS「おしるこ」のインサイト情報です。
おしるこは50代から利用できるSNSで、9万人の会員が、日々の出来事や興味関心のあることについて、日々発信しています。
まさに今、シニア層の流行や、どんな価値観を持っているかなど「生きた情報」を知れるのが、おしるこのインサイトなんです。
またおしるこでは、SNS広告や、商品やサービスをシニアに体験してもらえるサービスもあります。インサイト情報を活かしたPR戦略についてバックアップする体制も整っていますので、シニア向けマーケティングでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。
 お問い合わせ
お問い合わせ