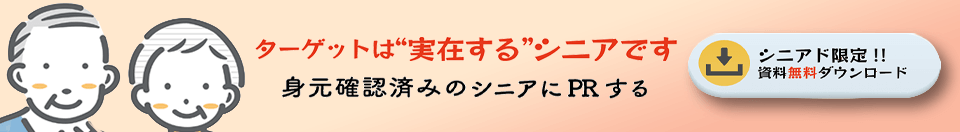シニアがノスタルジーを感じる映画に感動するのはなぜか?
シニアは、懐かしさを覚えるコンテンツに対して消費行動を起こしやすいと言われていて、そのような消費行動は「ノスタルジー消費」と呼ばれます。近年はノスタルジー消費を喚起してヒットするコンテンツが散見されていて、映画もその1つです。この記事では、ノスタルジー消費とは何か、なぜシニアにはノスタルジー消費をする傾向があるのか、そしてシニアがどのような映画に懐かしさを覚えるのかをご紹介します。
目次
1.ノスタルジー消費とは?
「ノスタルジー消費」とは、20歳頃までに体験した文化を、懐かしむ気持ちから生まれる消費行動です。
ノスタルジー(nostalgie)は、フランス語に由来する言葉で(英語ではnostalgia:ノスタルジアといいます)、故郷や過ぎ去った時代などを懐かしむことや、それらに対する懐かしさを指します。
人々がノスタルジーを感じる対象は、音楽、映画、文学、漫画、アニメーション、テレビ番組、食生活、建造物、街並み、乗り物、スポーツ、ファッションなど、さまざまです。
これらの懐かしさを感じる対象を欲する消費行動が、ノスタルジー消費ということになります。
例えば、NHKの朝の連続テレビ小説は、戦前・戦後や高度経済成長期といった昭和時代を舞台とした作品が、半分ほどを占めています。
これは、現在朝にテレビを見ている主な層が20歳頃までに過ごした時代、懐かしさを覚える時代が、昭和時代であり、彼らによるノスタルジー消費を狙っているためだと推測されます。
近年は、昭和末期や平成初期の映画やテレビアニメがリメイクされたり、続編が制作されたりしています。
多くの人が見るテレビのCMに、1990年前後のテレビゲームの曲が使われるというケースも、今や当たり前のように見られます。
参考1:岡田准一&生田斗真出演のアサヒスーパードライ「生ジョッキ缶」新TVCM公開、CM曲は「ロトのテーマ」 – ナビコン・ニュース
参考2:大塚製薬の新CM楽曲はサクラ大戦「ゲキテイ」 門脇麦コミケ同人作家役!富田望生スタッフ役 | ORICON NEWS
これらも、消費者にノスタルジーを感じさせる戦略だとみなしてよいでしょう。
2.ノスタルジーを感じさせるコンテンツはなぜシニアに受け入れられるのか?
ノスタルジー消費は、40歳以上の世代によくみられると言われています。シニアも例外ではありません。
その第一の理由として考えられるのは、年齢を重ねると脳機能が低下して、新しいことの学習に対するハードルが上がってしまうためです。特に、65歳にもなると、脳が委縮して物理的にも小さくなっていて、動作が緩慢になったり、物事を思い出すことが難しくなったりしてしまうことがわかっています。結果的に、新しいものよりも昔なじんだために勝手のわかるものを求める傾向が生まれ、これがノスタルジー消費につながります。
第二の理由は、昔なじんだことは、追体験効果が出やすいためです。若い時期の情動とは大きなもので、記憶に残りやすいです。ノスタルジーを感じるコンテンツを経験することで、人々は若かった当時の刺激的な気持ちの追体験を求めていると考えられます。特にシニアの場合は、退職や子育ての終了などによって、日常で刺激を感じる機会が減少する一方で自由な時間は増えているため、より刺激的な経験を求める行動をしやすい環境にあるといえます。
参考:世代特有のノスタルジー消費提供がカギ | 村田アソシエイツ | アクティブシニア市場を開拓したシニアビジネスの先駆者
第三の理由は、ノスタルジーには退屈、孤独、不安といった情動を和らげる効果があるためです。2020年に発生したコロナ禍においては、消費者が若い頃のテレビ番組や映画、歌といったコンテンツに安らぎを感じていたことがわかっています。先の見えない不確実な社会情勢において、人々は昔懐かしい、変わらないものに安らぎを見出すのでしょう。
参考:ノスタルジアマーケティングが注目される理由と具体的な事例について | TandemSprint|アメリカ進出・展開を目指す日本企業をサポート
シニアがノスタルジーを感じるコンテンツを提供するためには、ターゲットとするシニアがどのような文化を体験してきたかを知る必要があるでしょう。
各世代が20歳頃までに流行したものや、体験したできごとについては、下記の記事をご覧ください。
また、シニアがノスタルジーを感じるコンテンツは、若い世代にも受け入れられるケースがあります。Z世代といった若い世代の中には、自分が生まれる前の時代の文化に興味を持ち、自身のライフスタイルに取り入れる層が一定数いるのです。シニア世代のノスタルジー消費を狙ったコンテンツが、若い世代には逆に新鮮なものと認識され、彼らも消費者として取り込めると期待できます。
3.シニアにノスタルジーを感じさせる映画とは?
この記事では、シニアがノスタルジーを感じるコンテンツの1つとして、映画を想定します。日本で映画がエンターテイメントとして成立したのは大正時代のことで、テレビよりも歴史が長く、現在に至るまで洋画・邦画を問わずさまざまな映画が上映されています。そのため、どの世代であっても、若い頃の思い出となっている映画が存在するでしょう。また、ある程度有名な映画に限りますが、DVDのレンタルや配信などの方法で、昔の作品であっても比較的簡単に視聴できることも、映画というコンテンツの魅力といえます。
では、シニアにノスタルジーを感じさせる映画とはどのような映画でしょうか。1つには、シニアが若い頃にヒットした映画があげられます。もう1つには、シニアの若い頃の思い出を刺激するような内容の映画があげられるでしょう。
シニアが若い頃にヒットした映画
1950年代
1935年~1946年頃生まれの「焼け跡世代」が若い時期を過ごした1950年代には『雨に唄えば』『ローマの休日』といった映画がヒットしました。特に『ローマの休日』は「不朽の名作ラブコメディ」と呼ばれ、時代を超えて愛されています。
1960年代
1947年~1949年頃に生まれた「団塊世代」や、1950年~1965年頃に生まれた「しらけ世代」が若い時期を過ごした1960年代には『サウンド・オブ・ミュージック』『2001年宇宙の旅』といった映画がヒットしました。これらの映画も世代を超えて愛されているといえるでしょう。特に『2001年宇宙の旅』は、SF映画の古典とも称されており、史上最高レベルの映画として、公開当時から近年に至るまで高く評価され続けています。
1970年代
1955年~1967年頃に生まれた「新人類世代」や、1965年~1970年頃に生まれた「バブル世代」が若い時期を過ごした1970年代には『時計じかけのオレンジ』『ゴッドファーザー』『スター・ウォーズ エピソード4』『ポセイドン・アドベンチャー』『ジョーズ』『マッドマックス』といった映画がヒットしました。ヒットする映画の種類が多様化していく時期であったことがうかがえます。
1980年代
1971年~1974年頃に生まれた「団塊ジュニア世代」が若い時期を過ごした1980年代には『スタンド・バイ・ミー』『E.T.』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』『吉原炎上』といった映画がヒットしました。ヒットする映画の種類が、ますます多様化しています。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ターミネーター』『ダイ・ハード』といった、続編がいくつも作られた作品の第1作がこの時期に公開されてヒットしたことも特徴的です。
また『となりのトトロ』では、焼け跡世代や団塊世代が若かった時期である、1955年頃の日本の風景が描かれています。したがってこの作品は、次に示すシニアの若い頃を思い出させるような映画でもあると言えます。
シニアの若い頃を思い出させるような映画
公開されたのが近年の映画であっても、シニアが若かった時代の風景を描いたり、シニアの若い頃の思い出を刺激したりするような映画は、やはりシニアにノスタルジーを感じさせるといえます。
例えば、2005年に公開された、東京の下町に暮らす人々の交流を描いた『ALWAYS 三丁目の夕日』は、緻密なセットやVFX(映像効果)によって、1950年代の風景を見事に再現しました。その結果、当時あまり映画館で映画を見ないと言われていた40代や50代の男性を中心に大ヒットを記録したのです。2007年には続編の『ALWAYS 続・三丁目の夕日』、2012年には『ALWAYS 三丁目の夕日’64』が公開されています。
参考:映画「ALWAYS 三丁目の夕日」とVFXの意味 | 村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ
2022年に公開されて大ヒットした戦闘機アクション映画の『トップガン マーヴェリック』もまた、人々に若い頃を思い起こさせる映画だったと言えるでしょう。前作の『トップガン』が日本で公開されたのは1986年で、バブル世代や団塊ジュニア世代がまだ若く、団塊世代でさえも40代には達していなかった頃です。当時若かった人たちが、懐かしさや熱狂を味わいたいと考えて、映画館に足を運んだことは想像に難くありません。映画を見た人の中には、感動して涙を流す人や何度も見る人もいて、興行収入は137億円にも及びました。
参考:『トップガン マーヴェリック』が大成功したのは思い出消費? これからのヒットの秘訣はシニアの思い出の中にある | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
4.まとめ
シニアのノスタルジーを求める消費行動の強さや、シニアという消費者層自体の厚さは無視できないものです。ノスタルジー消費は、今後のシニアの消費行動を喚起する上で重要な要素の1つとなるでしょう。
シニアがどのようなコンテンツにノスタルジーを感じるかを知るためには、シニアのリアルな声を受け止めたいところです。SNSはそのために最適なツールの1つと言えます。SNSの1つである「おしるこ」は、会員の年齢が50歳以上に限定されているので、シニアのインサイトの把握を効率的に行えます。また「おしるこ」では利用している会員に向けて広告を出せるので、対象をシニア層に絞った効果的なPRが行えます。詳しい広告の詳細は以下よりダウンロードいただけますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
「シニアド」へのご相談を1クリックで予約しませんか?
シニア市場への理解を深め、効果的なアプローチをサポートいたします。マーケティング戦略、ブランディング強化など、ご検討中の課題をぜひお聞かせください。 専門スタッフが丁寧に対応いたします。
 お問い合わせ
お問い合わせ