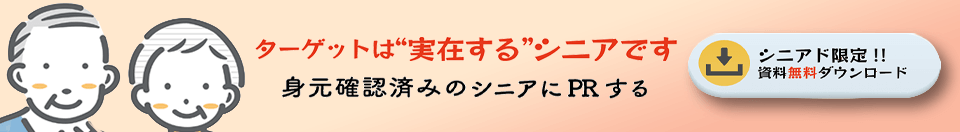高齢者の困っていること3選と対策!成功事例も交えて解説
高齢者の多くが健康、孤独、経済面での不安を抱えています。
そして、この問題は年々深刻化しており、私たちの親世代、そして将来の自分自身にも直結する課題となっています。しかし、AIやデジタル技術を活用した解決策や全国各地での成功事例が次々と生まれています。
この記事では、高齢者が直面する3つの主要な課題とその具体的な解決策を最新の取り組み事例と共にご紹介します。より良い高齢社会の実現に向けた、実践的なヒントが詰まっています。
目次
1.高齢者が日常生活で困っていること3選
高齢者が日常生活で困っている代表例は以下の3つです。
第1位:健康の維持と医療アクセス
第2位:社会的孤立や孤独感
第3位:経済的な不安
高齢者は健康や孤独感、経済的な面に不安を感じています。これらを1つずつ詳細に解説していきます。
第1位:健康の維持と医療アクセス
高齢者は加齢に伴う慢性疾患や体力低下により、定期的な医療ケアや健康管理が欠かせない状況です。たとえば、以下のような症状や病気が考えられます。
- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病の管理
- 骨粗しょう症や関節炎などの運動器疾患のケア
- 認知機能の低下予防 など
高齢者は複数の病気に対して受診をしなければならず、通院に困難さを感じているでしょう。内閣府が実施した「高齢者の住宅と生活環境に関する調査」によると、65歳以上の高齢者の23.8%が「医院や病院への通院に不便」を感じていると回答しました。
参照:第2章 調査結果の概要 -4 4.生活環境に関する事項 内閣府
第2位:社会的孤立や孤独感
一人暮らしの増加や家族との関係が疎遠になることで、日常的なコミュニケーションの機会が著しく減少しています。核家族化や地域コミュニティの希薄化により、かつては当たり前だった近所づきあいや世代間交流が減少し高齢者の孤立を加速させています。
さらに、長年の付き合いのある友人や知人の高齢化や死別により、社会的なつながりが徐々に失われていく高齢者も少なくありません。内閣府の調査によると、65歳以上の高齢者のうち、親しい友人や仲間が「たくさんいる」と答えた割合は、2024年時点でわずか7.8%であり、2018年の24.7%から大幅に減少しています。
この社会的孤立は、単なる寂しさだけでなく、認知機能の低下や鬱状態などの心身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
また、緊急時の助けを求められない、詐欺や犯罪の被害に遭いやすいなど安全面での課題です。特に都市部では、同じマンションの住人とも面識がないケースも多く、孤独死のリスクも指摘されています。
参照:令和6年度版 高齢者白書 第3節 〈特集〉高齢者の住宅と生活環境をめぐる動向について
The Impact of Loneliness and Social Isolation on Cognitive Aging: A Narrative Review
第3位:経済的な不安
年金受給額や手持ちの貯蓄だけでは、日々の生活費や継続的な医療費の支払いに不安を感じる高齢者が増加しています。特に、物価の上昇や医療費の負担増加により生活の質を維持することが困難になっているケースもあるでしょう。
また、突発的な介護費用や住居の修繕費など、予期せぬ支出への経済的な備えが十分でないことも大きな不安要因となっています。老後の生活資金として想定していた貯蓄も予想以上に長くなった平均寿命により、不足する可能性が高まっています。
さらに、子どもの教育費や住宅ローンの返済が継続している場合もあり、老後の経済的な余裕を失っているケースも少なくありません。加えて、高齢者の再就職は困難な場合が多く、収入を増やす手段が限られていることも、経済的な不安を増大させる要因となっています。
2.高齢者の困りごとを解決した成功事例
高齢者の困りごとを解決した成功事例について以下の項目について紹介します。
- 健康食品メーカーの取り組み
- 地域でのデジタル教室の成功例
- コミュニティイベントでの孤独感解消
高齢者の困りごとに対して、成果を上げたものを理解することで、今後の高齢者支援をより効果的に進めることができます。それぞれの事例から得られた知見を活かし、新たな取り組みの参考にしていきましょう。
健康食品メーカーの取り組み
株式会社明治は、高齢者の栄養摂取問題に着目し「明治メイバランス」シリーズを展開しました。「明治メイバランス」シリーズは加齢による食欲低下や栄養不足に対応するため、たんぱく質やビタミン、ミネラルをバランスよく配合しています。

飲みやすい容器デザインや多様な味があり、高齢者が日常的に摂取しやすい工夫を施しています。また、販売戦略として、従来の小売店だけでなく訪問介護ステーションや地域包括支援センターなどの介護関連施設への展開が特徴的です。
参照(画像):株式会社 明治
地域でのデジタル教室の成功例
茨城市では、地域住民のデジタルスキル向上を目的に、学校やコミュニティセンターでデジタルリテラシー教育プログラムを実施しています。このプログラムでは、特に初心者や高齢者を対象に、インターネットの基本的な使い方や安全な利用方法を丁寧に指導しています。
また、低所得者や高齢者向けにデジタル機器を貸し出しており、経済的な負担を軽減する取り組みを行っています。この結果、地域住民のデジタル技術へのアクセスが向上し、オンライン行政サービスの利用や地域活動の活性化が進みました。
参照:茨城県認定リスキリング教育プログラム「デジタルリテラシー実践講座」
コミュニティイベントでの孤独感解消
富山県では、オンラインコミュニティ「ウェルビーイング・コミュニティとやま」を通じて、地理的制約を超えた交流を実現しています。
ウェルビーイング・コミュニティとやまは、富山県が運営する無料オンラインコミュニティです。県民の幸福度向上と地域活性化を目指し、Slackを活用したオンライン交流や定期的なイベント開催を行っています。
特徴的なのは、身体的・精神的健康、経済的余裕、社会的つながりなど7つの要素からなる「ナナイロ指標」を用いて住民の幸福度を可視化している点です。県内外での交流イベントやプロジェクトを通じて富山の魅力を発信し人口の拡大も目指しています。
参照:ウェルビーイングを充実させるためのコミュニティの重要性 PCA
3.高齢者の困りごとに対応する新しいトレンド
高齢化社会が進む中、高齢者が抱える日常生活での困りごとに対して最新のテクノロジーを活用した解決策が次々と生まれています。従来の介護サービスや支援制度に加え、デジタル技術を駆使した新しいアプローチが、高齢者の自立した生活と生活の質の向上に貢献しています。
特に注目すべきは以下の項目です。
- AIの活用
- 金融・買い物支援
- オンラインコミュニティ
3つの分野での取り組みを解説します。
AIを活用したサービス
人工知能(AI)技術を活用した高齢者支援サービスは転倒防止が可能です。たとえば、AIを活用して高齢者の歩行状態を分析し、転倒リスクを軽減するサービスがあります。スマートフォンのカメラで歩行を撮影し、AIが歩行速度やリズム、ふらつきなどを数値化して改善策を教えてくれます。
「CareWizトルト」というアプリでは、理学療法士の知見を学習したAIが歩行データを分析し、適切な運動を提案することで高齢者の自立支援が可能です。
また、スマートフォンやタブレットで利用できる健康管理アプリは、AIが利用者の年齢、持病、運動習慣などの個人データを分析してくれます。「血圧ノート」というアプリは、血圧や体重などを記録しかかりつけ医にデータを見せる際に活躍します。
金融・買い物の利便性向上
デジタル決済の普及に伴い、高齢者でも安心して利用できる電子マネーやスマートフォン決済サービスが開発されています。たとえば、大きな文字表示と音声ガイダンス機能を備えた専用アプリでは、支払い手順を3ステップ以内に抑え、誤操作防止機能や利用限度額の設定機能も搭載しています。
また、地域の商店街と連携した移動スーパーではタブレットを使って事前に注文を受け付けることができます。決まった時間に自宅近くまで商品を届けてくれるため非常に便利です。さらに、生鮮食品から日用品まで、地域の複数の店舗の商品をまとめて配達する統合型の宅配サービスも登場し買い物の負担を大幅に軽減しています。
オンラインコミュニティの活用
高齢者の孤立防止と社会参加を促進するため、使いやすさを重視したオンラインコミュニティプラットフォームが開発されています。専用のSNSでは、書道や園芸、料理など共通の趣味を持つ利用者同士が作品や栽培のコツを共有したり、オンライン上で講座を開いたりすることができます。
また、地域密着型のデジタルプラットフォームでは町内会や老人会の活動をオンラインで補完し、天候や体調に関わらず参加ができます。地域の防災情報や行事案内の配信、オンラインでの健康体操教室の開催、さらには地域の歴史や文化を次世代に伝えるデジタルアーカイブの作成など、多様な活動が展開されています。
「おしるこ」は、50歳以上のシニア層を対象としたSNSアプリです。シニア世代が日常生活や趣味、経験を共有するためのコミュニティを作ることができます。企業がシニア層に向けたマーケティング活動を展開する場としても活用されています。
「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。
「シニアド」へのご相談を1クリックで予約しませんか?
シニア市場への理解を深め、効果的なアプローチをサポートいたします。マーケティング戦略、ブランディング強化など、ご検討中の課題をぜひお聞かせください。 専門スタッフが丁寧に対応いたします。
 お問い合わせ
お問い合わせ