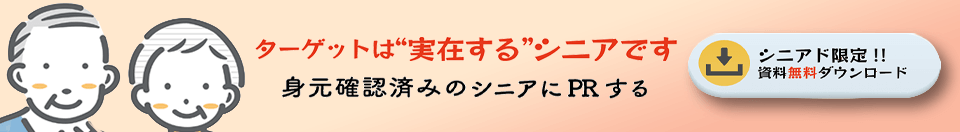終身支援サービスの拡大と事業者に求められる姿勢:超高齢化社会への対応策
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、65歳以上人口は、3,624万人。総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は29.3%となります。
このため、加齢により日常生活や資産管理が難しい方へのサポートとして「終身支援サービス」の需要が急増しています。
本記事では、サービスを提供する企業にとって、ますます重要になるシニアサポートの在り方と、国が定める「終身サポート事業者」のガイドラインに基づく対応などについて解説します。
参照:令和7年版高齢社会白書
目次
- シニアサポートの現状とニーズの拡大
- 「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」について
- ガイドラインに基づく事業者に求められる姿勢や役割
- これからのシニアサポート事業者に必要な取り組みや対策
- まとめ|シニア層との信頼構築に、SNSの利用がおすすめ
1.シニアサポートの現状とニーズの拡大
シニア層が直面する課題
日本の高齢化が進む中で、シニア層が抱える課題はますます複雑化しています。
具体的には、身体的な健康問題はもちろん、認知症を抱える高齢者は2022年に443.2万人となっていますが、2060年には645.1万人になるという見込みです。
要介護・要支援の認定を受ける要介護者は、令和2年度末現在682万人で、この21年間で約2.7倍に。日常生活での支援が不可欠な高齢者が、今後も増加していくことは明白です。参照:厚労省
また、単身のシニアも増えており、2020年に671.7万人だった1人暮らしのシニアの人口は、2040年に896.3万人となる見込みです。参照:日本生命
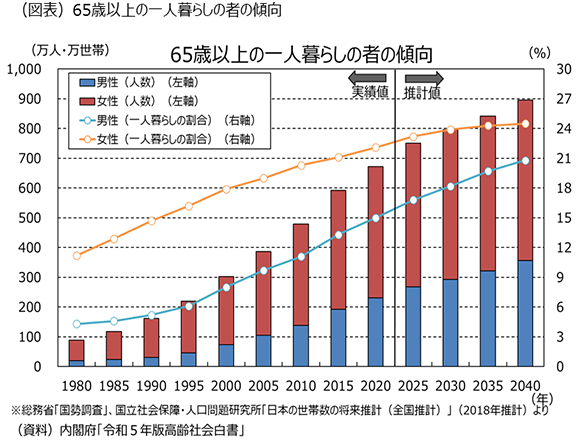
単身のシニアは社会的な繋がりを失うケースも多く、孤立が深刻な問題となっています。
シニアが孤立せず社会活動への参加することは、生活への充実感や生きがい、心身の健康に繋がるため、対策が必要です。
シニアが抱える悩みについての詳しい解説は、こちらの記事も参考にしてください。
多様化するニーズへの柔軟な対応
シニア層のニーズは健康状態や生活環境などによって変わり、多様化しています。
例えば、健康な高齢者には、趣味や社会活動の機会を提供することが重要であり、要介護状態のシニアには日常生活の支援が必要です。
また、現代では特に身元保証人がいなくて入院や手術ができないなどのトラブルになるケースもあり、適切かつ柔軟なサポートが求められています。
健康状態や生活環境に応じた包括的な支援が、シニアの生活の質を高める鍵となります。
参照:高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として-結果報告書 関東管区行政評価局
終身支援サービスの注目
こうした中で、シニア層の多様なニーズに応える「終身支援サービス」が注目されています。
このサービスは、シニアの健康な時期から介護が必要になる段階まで、生涯にわたって適切なサポートを提供するものです。
財政や人手不足などの要因で公的支援だけではカバーできないサポート部分を、民間企業をはじめ、医療法人・社会福祉法人などが、介護や見守りサービス、保険商品など個々に合わせた多岐にわたるサポートで補うことが期待されています。
包括的なサービスが提供されている中で、利用者は安心して暮らしていくために、自分に必要なものを選択することが可能です。
2.「高齢者等終身支援サポート事業者ガイドライン」について
日本の高齢化が進む中、シニア層を支える福祉サービスの重要性が高まっています。
国が策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、シニア向けサービスの安全性と信頼性を確保するための指針として位置付けられています。
このガイドラインの背景や主な内容を詳しく見ていきましょう。
ガイドライン策定の背景と目的
日本は高齢化が進行している国の一つであり、シニア層に対する終身支援サポートの重要性が増しています。
そのため、終身支援サービスのニーズは今後も増加が予想されますが、サービス内容はさらに包括的になり、複数の法律に関わる業務が増えることが考えられます。
そのため、国は事業者が守るべき法的規定や注意すべき点などを整理し2024年に「高齢者等終身支援サービス事業者ガイドライン」を策定しました。
このガイドラインの目的は、シニア向けの福祉サービスの安全性と信頼性を高め、利用者が安心してサービスを受けられるようにするための基本的な基準を設けることです。
また、高齢者に提供される福祉サービスの拡大に対して、適切なサービス提供が行われることを目指し、事業者の運営指針を明確にしています。
終身支援サービスの安全性と透明性
ガイドラインでは、主な対象を「身元保証サービス」及び「死後事務サービス」を提供する事業所とし、事業者が提供するサービスにおいて、安全性と透明性が特に重視されています。
シニア層は、長期間にわたってこれらのサービスを利用することが多いため、安心して利用できる環境が必要です。
具体的には、介護サービスの質の確保、契約内容の明確化、料金体系の透明性が基本的な要素として挙げられます。
合わせて、定期的な面談や必要な情報の提供などで利用者の自己決定が行えるよう配慮し、信頼を寄せられるサービス環境が整備されることが期待されています。
倫理規範と運営基準のポイント
ガイドラインには、事業者が守るべき倫理規範と運営基準が詳細に記されています。
これには、シニア層に対する公平で誠実な対応や個人情報の適切な管理、緊急時の対応マニュアルの整備が含まれます。
この基準は、事業者が倫理的に正しい行動をとることを保証し、サービス提供の透明性を確保するためのものです。
また、不適切な対応があった場合や問題発生時の責任についても明確にされており、事業者の信頼性を高めるための重要な内容となります。
参照:高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドラインについて 消費者庁
3.ガイドラインに基づく事業者に求められる姿勢や役割
シニア向けサービスの質を保つため、事業者は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守することが求められます。
このガイドラインに基づく信頼関係の構築やリスク管理は、利用者の安心感を高める上で重要です。
事業者に求められる具体的な姿勢と役割について見ていきます。
信頼関係の構築とサービスの質の維持
ガイドラインに基づく運営を行う上で、事業者が重要視するべき点は、シニア層との信頼関係を築くことだと言えます。
シニアは、生前から死後にわたるまで長期間にわたってサービスを利用することが多いため、事業者との関係が一度築かれると、信頼してその関係が維持できることが重要だからです。
信頼関係を構築するためには、常に誠実な対応と高いサービスの質を提供し続けることが不可欠です。
従業員の定期的な研修や、変化するニーズに合わせた支援プランの見直しなど、サービスの質を維持し、利用者が安心して頼れる環境を提供することが求められます。
リスク管理と法令遵守の重要性
シニアサポート事業において、リスク管理と法令を遵守することは、事業者の大切な責務です。
個人情報保護や法的リスクの管理はもちろん、倫理的リスクも含めて慎重に対応する必要があります。
シニアは特に社会的に脆弱な立場に置かれることも多く、適切なサポートが行われなかった場合、身元保証人がいないために入院手続きができなかったり、遺族が相続手続きに苦労したりするなど、大きな問題となる可能性が高いです。
そのため、事業者は法令をしっかりと遵守し、適切なリスク管理を行うことが求められます。
具体的には、個人情報保護法に基づいた厳しいデータ管理や、トラブル発生時の迅速な対応策の準備などです。
マーケティングにおけるガイドライン活用
ガイドラインの策定は、事業者にとって信頼性を強調するためのマーケティングの一環としても活用できます。
利用者やその家族に対して、ガイドラインへの準拠を示すことで、安心感を与えることができ、他の事業者との差別化にもつながるでしょう。
特に、運営の透明性や高い倫理基準に従っていることがアピールできれば、利用者の信頼を得るだけでなく、地域社会や行政との連携を深めることも期待できます。
4.これからのシニアサポート事業者に必要な取り組みや対策
今後のシニアサポート事業者には、変化・多様化するニーズに適応するための取り組みが求められています。
特に、デジタル技術の導入や地域コミュニティとの連携強化が重要です。
これにより、シニア層の生活の質を向上させ、信頼関係を築くことが可能になります。
具体的な戦略について見ていきます。
デジタル技術を活用した新しいサポートサービス
今後の高齢者支援の市場は、日本の高齢化が進んでいくに従って多様化・拡大が予想できます。
シニア層のニーズに応えるためには、デジタル技術を活用した新しいサポートサービスも不可欠です。
特に、リモートヘルスケアやウェアラブルデバイスを用いた、便利で手軽な健康管理も重要となるでしょう。
また、シニア同士のコミュニティ形成やニーズの把握においては、シニア向けSNSの活用が有効であり、社会的なつながりも促進します。
その理由は、シニア層のSNS利用について、60代は73.4%、80歳以上も53.8%と利用者が多いためです。
こうした取り組みは、事業者が利用者と信頼関係を構築し、質の高いサービスを維持するためにも重要です。
シニア市場の動向については、こちらの記事でその見通しやマーケティングのポイントなどを解説しています。気になる方はぜひ参考にしてみてください。
地域コミュニティとの連携強化
シニア層の社会的孤立を防ぐためには、利用者が居住する地域コミュニティや自治体との連携が特に大切です。
地域でのサポート体制を強化し、シニアが社会的に孤立しない環境をつくるためには、ボランティアや地域住民との協力が重要となります。
地域でのシニア向けイベントや支援プログラムを活用し、シニアがコミュニティの一員として活動できる環境を整えることが求められます。
5.まとめ|シニア層との信頼構築に、SNSの利用がおすすめ
シニアサポート事業者には、今後ますます高まるニーズに対応するための柔軟性と責任が求められています。
国が策定した「高齢者等終身支援サービス事業者ガイドライン」に基づき、安全で信頼性の高いサービスを提供することが、事業者にとっての基本的な責務です。
また、今後のシニアサポート業界は、シニアの生活の質を向上させるための多様な取り組みを進める必要があります。
そのためには、事業者が変化を受け入れ、新しいサービスやマーケティング戦略を展開していく姿勢が求められます。
その一環として、シニア専用SNS「おしるこ」の利用がおすすめです。
「おしるこ」は、50歳以上の方に特化したプラットフォームで、利用者は約9万人、シニア層の信頼を得るためのマーケティング基盤となります。
このSNSを通じて、シニア同士のつながりを強化し、多様なニーズを把握することが可能です。
広告利用を通じて、事業者はシニア層に直接アプローチできるため、より効果的なサービス提供も実現します。
「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。
「シニアド」へのご相談を1クリックで予約しませんか?
シニア市場への理解を深め、効果的なアプローチをサポートいたします。マーケティング戦略、ブランディング強化など、ご検討中の課題をぜひお聞かせください。 専門スタッフが丁寧に対応いたします。