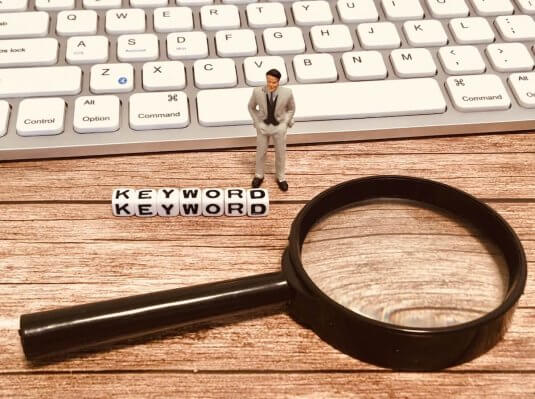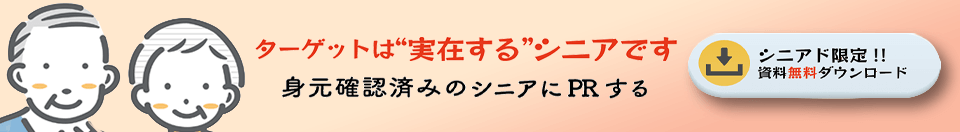高齢者が台風災害時に困ることは?逃げ遅れを防ぐための対策を紹介
台風の発生・接近・上陸ともに、10月にかけて最も多くなります。そこで、台風に対して、高齢者はどのように対策すべきなのでしょうか?本記事では、台風がきたときに高齢者が困ることや、対策について解説します。
目次
- 高齢者が災害時に困ることは?
- 台風が来る前に備えておくことは?
- 避難できない?台風から逃げ遅れないためのポイント
- 避難所生活で高齢者が困ること
- 災害時対策にSNS活用がオススメな3つの理由
- 高齢者の災害対策に関するよくある質問
- まとめ
1.高齢者が災害時に困ることは?

高齢者が災害時に困ることを把握しておきましょう。
高齢者が災害時に困ること
- 判断が遅れ逃げ遅れるケースが多い
- 素早く避難できない
- 避難所生活に馴染めない
何に困るかを具体的に把握しておけば、対策しやすくなります。以下の内容を参考にしながら、実際に台風がきたときを想定して、今後の災害対策に活かしていきましょう。
判断が遅れ逃げ遅れるケースが多い
高齢者は、それまでの経験から「自宅にいれば大丈夫」と考える方が多くいます。
特に、近所の人々が避難していないと、自分も避難しなくて大丈夫だろうと考えがちです。
さらに、認知能力が低下していた場合、判断が遅れて逃げ遅れる可能性が高まります。
こうした危機意識の低さや、認知能力の低下などによって逃げ遅れてしまい、状況が悪化してしまうケースが少なくありません。
素早く避難できない
特に多くの人が困るのが、移動です。
高齢者は運動能力が低下しているため、若い人のように素早く避難ができません。
家屋倒壊や津波など、緊急避難が求められる場面では、周囲もどうすべきか判断に迷ってしまいます。
2011年の東日本大震災では、高齢者が逃げ遅れたり、助けようとした若者が一緒に流されたりと悲惨な被害が多くありました。
また、認知機能が低下している方だと、適切な判断ができず、その場に留まってしまうケースも多くあります。
こうした運動機能や認知機能の低下による逃げ遅れは、二次被害を引き起こす原因にもなっています。
避難所生活に馴染めない
高齢者は、住み慣れた土地や家でとても長い時間を過ごしています。
そのため、急激な生活環境の変化に対応できない方が少なくありません。
周囲の音や、使い慣れていない寝具、今までと異なる生活ルールなど、さまざまな部分でストレスを感じます。
また、知らない人と関わる機会が増えることも、ストレスを感じる一因になるでしょう。
もちろん若い方でもストレスは感じますが、高齢な方ほど環境変化への対応は難しいケースが多いとされています。
2.台風が来る前に備えておくことは?
台風が来る前に、以下のチェックリストを見ながら準備をすすめましょう。
台風が来る前の準備チェックリスト
- 連絡手段について話し合う
- 防災セットを整理する
- 物干し竿や植木鉢をしまう
- 雨戸やシャッターを閉める
- 生活用水を確保する
- モバイルバッテリーを充電しておく
それでは、具体的に何をどう準備すればよいのか、以下で解説します。
連絡手段について話し合う
まずやって欲しいのが、連絡手段について話し合っておくことです。
台風が来ると、停電や機器故障によって連絡が取りにくくなることがあります。
いくつかの連絡手段を確保したうえで、それぞれの使い方を確認しておきましょう。
スマホ・PC・タブレットのほか、昨今では「見守りカメラ」を活用するケースも多くあります。
防犯カメラのようなもので、高齢者の様子を確認できるアイテムです。
連絡手段として活用したい場合には、会話機能付きの機種を選択しましょう。
防災セットを整理する
防災セットは、定期的に整理しておきましょう。
放置してしまうと、非常食が賞味期限切れになっていたり、ライトやラジオの電池が切れていたりします。
以下のアイテムが入っているか、それぞれの使用期限や状態に問題がないかを毎年チェックしてください。
防災セットに入れておくもの
- 水
- 食べ物
- 着替え、タオル
- ティッシュ、ウェットティッシュ
- レインコート
- 軍手
- ヘルメット
- ビニール袋
- 常備薬、マスクなどの救急用品
- 保険証、お薬手帳
- ライト
- 携帯ラジオ
- 笛(枕元に置いておくのもOK)
- ライター、マッチ
- 電池、モバイルバッテリー
- スリッパ
なお、中身を多くしすぎると、重すぎて高齢者が持ち運びにくくなります。
実際に背負ってもらって、問題なく避難ができるかも確認してください。
物干し竿や植木鉢をしまう
台風が来ることが予想されている場合、すぐに屋外の物をしまってください。
どれだけ重たい物でも、台風の強い風によって吹き飛ばされる可能性は十分あります。
物が飛ばされると、家屋が破損したり、避難経路が塞がれたりして危険です。
雨風が強くなってからだと、しまうのが大変になるので、晴れているうちに作業を済ませましょう。
高齢者が自力で動かせないものに関しては、近所の人や親族が強力して移動させてください。
雨戸やシャッターを閉める
家の中で台風に備える場合には、雨戸やシャッターを閉めましょう。
台風がくるのに、窓ガラスをむき出しにしているのは大変危険です。
飛んできた物によって、窓ガラスが割れ大けがをする可能性があります。
台風の風は非常に強力で、カバンや靴、本などであっても、窓ガラスを貫通させるほどの力があるのです。
また、自宅の網戸が飛ばされてしまい、ほかの家屋を傷つけてしまうケースもあります。
台風がくる場合には、早急に雨戸やシャッターを閉め、網戸と窓ガラスを守りましょう。
生活用水を確保する
台風がきたときに困るのが、断水です。
風雨による停電や、大雨による水道管の破損、取水施設の停止などにより、水が出なくなる被害は多く確認されています。
大きめのタンクを用意して飲み水を確保する、バスタブに水を溜めておくなどして、生活用水を確保してください。
なお、あまりにも早くから水を溜めておくと、衛生的に良くありません。
基本的には、実際に台風がくる1日〜半日前くらいに貯めておけば良いでしょう。
モバイルバッテリーを充電しておく
スマホを使う場合は、モバイルバッテリーの充電を満タンにしておきましょう。
台風がくると数日〜1週間ほど停電する可能性があるため、2〜3個のモバイルバッテリーがあると安心です。
最近は数千円でも十分な容量のモバイルバッテリーが購入できるので、ケーブルとあわせて購入しておきましょう。
3.避難できない?台風から逃げ遅れないためのポイント
災害時には、高齢者の逃げ遅れが問題になります。この逃げ遅れは、運動機能の低下だけが原因ではありません。認知能力やこれまでの経験、自宅や貴重品への思い入れなど、さまざまな原因が絡み合って発生しています。
台風から逃げ遅れないためのポイント
- 明るいうちに避難する
- 「高齢者等避難開始」で避難を開始する
- 貴重品と防災セット以外は持たない
- 天候が明確に変化してからでは遅い
この後の項目では、台風から逃げ遅れないための4つのポイントを解説します。
明るいうちに避難する
夜間に台風がくる場合であっても、日没前に避難してください。
夜間かつ悪天候のなかでの避難は、若者であってもケガをするケースがあります。
車で避難する場合、視界不良で思ったように避難できないかもしれません。
昼間に避難すれば、何かトラブルがあっても、周囲の人が気付いてくれる可能性が高まります。
季節によりますが、17時までに避難先に着く想定で避難を開始しましょう。
「高齢者等避難開始」で避難する
高齢者の方は「高齢者等避難開始」で避難を開始してください。
避難情報は、以下の流れで発令されます。
避難情報の段階
- 避難準備・高齢者等避難開始
- 避難勧告
- 避難指示
注意したいのは「避難指示で避難すれば良い」といった誤った解釈です。
避難勧告は全員が避難を開始するとき、避難指示は発災間近で命を守る行動をとるときです。
避難指示が出たタイミングは、洪水や土砂崩れがいつ起きてもおかしくないタイミングであり、ここで避難するのは遅すぎます。
高齢者の方は、必ず高齢者等避難開始のタイミングで避難を開始しましょう。
貴重品と防災セット以外は持たない
特に車移動の場合、不安でいろいろと持ち出したくなるでしょう。
しかし、緊急事態では一分一秒の迷いが命取りになります。
また、前提として「いろいろ持って行こう」と考えていると、忘れ物を取りに戻ってしまう可能性が高まります。
浸水や土砂崩れの危険が差し迫っている状態で、家に引き返すのは、命を危険にさらす行為です。
こうした危険な行為をしないためにも、あらかじめ「避難するときは貴重品と防災セットだけ」と決めておきましょう。
貴重品も、お財布・身分証・スマホと細かく決めておき、貴金属類や写真などは置いておくようにしてください。
天候が明確に変化する前に避難する
台風が到来すると、急速に天候が悪化します。
「雨風が強くなってきたな」「雨が溜まっているな」と感じたら、避難するには遅いと考えましょう。
天候が変わる前から避難を開始して、天候に異変を感じる前に、避難先に到着しているのが理想です。
「避難するほどじゃなかった」と思えたなら、それは生きている証拠。
ギリギリで避難をして命を危険にさらすのではなく、早すぎるくらいの意識で行動しましょう。
参考:高齢者はどうしたら災害時きちんと避難できるのか?(シニアド)
4.避難所生活で高齢者が困ること
逃げ遅れせず避難できても、その後の避難所生活では長く苦しい生活が続くかもしれません。特に、以下のような点で困る高齢者が多くいます。
避難所生活で高齢者が困ること
- 持病の治療ができない
- 生活環境の変化に対応できない
- エコノミークラス症候群になる
- 脱水になりやすい
- 孤立しやすい
- 脱水や感染症になりやすい
- 生活不活発病になりやすい
- 情報収集がしにくい
心身の病気を発症するケースも多くあるので、以下をしっかりと読んで、対策していきましょう。
持病の治療ができない
高齢者の困りごととして非常に多いのが、持病が悪化してしまうというものです。
避難時に薬や医療器具を置いてきてしまい、医療体制も整っておらず、体調が悪くなるケースが多くあります。
また外科的な持病で、専用の器具によるリハビリをしていた場合、長期に渡って治療が困難になるでしょう。
持病が悪化しないように、あらかじめ防災セットの近くに薬を置いておいたり、医師に相談したりといった対策が必要です。
周囲の声や物音がストレスになる
避難所での生活では、周囲の音が気になってストレスを感じる場合が多くあります。
年齢関係なくストレスは感じますが、特に高齢者は生活環境の変化に対応するのが難しいのです。
運動能力が低下していると、気晴らしに外に出るのも難しいため、余計にストレスが溜まります。
結果として、後述するような頻尿や持病、生活不活発病にもなりやすくなるでしょう。
頻尿・脱水になりやすい
ストレスの多い避難所生活では、頻尿が悪化する高齢者が多くいます。
尿意を伝える神経が過敏になったり、自律神経の乱れで尿意を感じやすくなったりするためです。
周囲の音や環境変化のみならず、トイレへ行きにくいという心理的ストレスも、頻尿に繋がります。
こうした頻尿を放置すると、水を飲まなくなっていき、脱水やエコノミークラス症候群を引き起こすため大変危険です。
周囲の人が、定期的に声かけをしたり、トイレへの導線を確保したりする対策が求められます。
エコノミークラス症候群になる
狭い場所で動かない時間が長引くと、エコノミークラス症候群を発症する確率が高まります。
エコノミークラス症候群とは、飲食を十分にせず長時間じっとしていた場合に、血液が固まって肺動脈に詰まってしまう病気です。
避難所生活では動き回ることが難しいのに加え、トイレに行きにくくなるため、水分を取らずエコノミークラス症候群になりやすくなってしまいます。
足のむくみ、息切れ、胸や背中の痛みなどを感じたら、早急に周りの人に相談してください。
また予防のために、定期的な運動やマッサージのほか、こまめな水分補給を行いましょう。
孤立しやすい
避難所には近くに知っている人がいないことが多く、孤立しやすいでしょう。
避難所の環境に慣れていないうえ、周囲の人も余裕がないため、新しいコミュニティを築きにくいのです。
近くに知人がいても、お互いに余裕がないために口論になって、人間関係が悪化してしまうケースもあります。
孤独感によるストレスが強くなると、認知症の発症・悪化に繋がる可能性もあるため、早急な対策が必要です。
この後の項目で紹介するようなSNSを活用すれば、孤独感の緩和に繋がります。
生活不活発病になりやすい
生活不活発病とは、生活での動きがなくなることで、脳機能や身体能力が低下して発症する病気の総称です。
具体的には、以下のような病気があげられます。
生活不活発病の主な症状
- 起立性低血圧
- 消化器機能の低下
- 便秘
- 食欲不振
- 関節痛
- 筋力低下
- 皮膚萎縮
- 静脈血栓症
- うつ
- 自律神経不安定
生活不活発病になると、余計に身体を動かすのが大変になり、症状が悪化する負のループに陥ってしまいます。
兆候を感じたら、定期的な運動を促すなど、早期の対策が重要です。
情報収集がしにくい
高齢者は若者ほどネットに慣れていないため、情報収集に苦労することも多くあります。
自分の住んでいる地域はどうなっているのか、いつまで避難所生活が続くのかなど、情報が入ってこないために不安が大きくなることも多いでしょう。
避難所にも情報は入ってくるものの、情報掲示板を見に行くのが大変といった理由で、なかなか情報を見に行けない方も少なくありません。
そのため、後述するようにSNSを活用して、日頃から情報収集ができる状態を整えておく必要があります。
5.災害時対策にSNS活用がオススメな3つの理由

災害時には、SNSを活用するのが非常におすすめです。SNSアカウントを作っておけば、台風をはじめとした災害に見舞われた際、以下のようなメリットがあります。
災害時対策にSNS活用がオススメな3つの理由
- 電子機器に慣れるきっかけになる
- 友人達と励まし合える
- 情報収集がしやすい
高齢者のなかには、SNSに対して抵抗感のある方もいるかもしれません。以下の内容を参考にして、SNS活用を進めてみてはいかがでしょうか。
電子機器に慣れるきっかけになる
日頃からSNSを使っていると、スマホに慣れるきっかけになります。
デジタルネイティブではない世代は、とにかく長い時間デジタル機器に触れて慣れることが大切です。
しかし、トレーニングのような意識でスマホを使おうとしても、目標がなく続きません。
そこでおすすめなのが、SNSを活用してスマホに慣れていく方法です。
SNSではたくさんの人々と触れあえるため「また使いたい」と主体的にスマホを使うようになります。
結果として、災害時でも問題なくスマホを使えるくらい、電子機器に慣れておけるでしょう。
友人達と励まし合える
ネット上で繋がった友人達と励まし合えるのも、SNSを活用するメリットです。
避難所では知り合いと話す機会が減ってしまい、孤独を感じることが多くなります。
しかしSNSを使っていれば、その場で友人達と繋がれるので、孤独感を和らげられるのです。
フォロワーから励まされ、また自分も友人を励ますという良い循環が、自分自身のメンタルを健全に保ってくれます。
情報収集がしやすい
SNSでは、さまざまな人が情報発信をしています。
どの地域で何が起きているのか、情報を簡単に入手できるのもSNSの魅力です。
もちろん、嘘の情報が出回る可能性もあるため、正しい情報か見極めるネットリテラシーは必要になります。
しかし、手元で簡単に情報収集ができるのは、避難所生活において大きなアドバンテージになるでしょう。
シニアSNS「おしるこ」では、不審な情報を検知するための監視体制を整えているので、安心してご利用いただけます。
6.高齢者の災害対策に関するよくある質問
高齢者の災害対策について、以下のような疑問を抱く方が多くいます。
高齢者の災害対策に関するよくある質問
- 避難所に持病の薬を忘れてしまったら?
- SNSで誤情報に惑わされないためには?
- 災害関連死とは?対策は?
- 災害用伝言ダイヤルの使い方は?
よくある4つの質問について、以下で詳しく回答していきますので、ぜひ参考にしてください。
避難所に持病の薬を忘れてしまったら?
持病の薬を忘れてしまった場合、避難所に訪れた医療従事者に相談してください。
まだ医療支援チーム等が来ていない場合、まずは避難所の担当者に相談しましょう。
医療機関と連携して、薬を処方してくれる可能性があります。
しかし、災害時にはインフラや医療機関にも被害が出ていて、すぐに薬が入手できない可能性もあります。
防災バッグと持病薬はセットにして置いておき、避難時に忘れないようにしましょう。
SNSで誤情報に惑わされないためには?
SNSで誤情報やデマに惑わされないために、以下のポイントを意識しましょう。
SNSで誤情報やデマに惑わされないための対策
- 発信者が信頼できる人物かを調べる
- ほかにも同様の情報を発信している人がいるか調べる
- 情報がいつ発信されたものか調べる
- 政府や公共機関が発信しているかを調べる
- 情報の出所を調べる
大切なのは、誰が発信しているのか、情報の出所はどこかです。
著名人が発信していたとしても、情報の出所がネット掲示板では信頼性がありません。
また政府発表の情報だと書いていても、誰だか分からない人が発信している場合、そもそも政府発表の情報ではない可能性があります。
発信者と情報の出所どちらも信頼性があるか、ほかにも多数のメディアが正しい情報として扱っているかなどを判断軸とすれば、フェイクニュースに騙されにくくなります。
しかし、昨今ではデマやフェイクニュースの拡散方法も巧妙になってきています。
特に災害時はデマが広まりやすいので、情報を得てもすぐに拡散せず、少し時間をおくのが良いでしょう。
災害関連死とは?対策は?
災害関連死とは、災害時の被害そのものではなく、避難先でのストレスや運動不足などによって亡くなってしまうことです。
具体的には、以下のような事例が報告されています。
災害関連死の具体的な事例・死因
- 避難中の車内で疲労による心疾患
- 震災後の疲労等による心不全
- 不慣れな避難所生活によるストレス等で肺炎
- 地震の疲労による交通事故
- 避難先でのエコノミークラス症候群
- 地震のショックや余震への恐怖による急性心筋梗塞
災害関連死を防ぐためには、心身のケアをし続けるのが大切となります。
こまめに運動する、家族・友人・周囲の人と会話をするといった対策がおすすめです。
また持病のある方は、おくすり手帳を持参しておくのも、持病の悪化による災害関連死を起こさないために重要でしょう。
災害用伝言ダイヤルの使い方は?
災害用伝言ダイヤルとは、NTTが提供する災害時サービスです。
音声メッセージを録音したり、確認したりでき、伝言板のようなかたちで使えます。
具体的には、以下の流れで利用します。
災害用伝言ダイヤルの使い方
- 録音するとき
- 171にダイヤル
- 1をプッシュ
- 自宅の電話番号、または連絡を取りたい被災地の方の電話番号をプッシュ
- ※プッシュ式電話の方は再度1をプッシュ
- ガイダンスに従ってメッセージを録音
- 確認するとき
- 171にダイヤル
- 1をプッシュ
- 自宅の電話番号、または連絡を取りたい被災地の方の電話番号をプッシュ
- ※プッシュ式電話の方は再度1をプッシュ
- メッセージを確認
なお、平常時にはサービスを提供しておらず、災害時のみ利用可能になります。
災害時はネット回線が不安定になるケースもあるので、上記をスクリーンショットしておいたり、メモしたりして、使い方を覚えておきましょう。
7.まとめ
台風がくると分かったら、防災セットや持病薬の整理を行いましょう。台風の速度は常に変化していて予測が難しいため、早めに対策しておくのが大切です。
避難所生活では、孤独感や災害に対する恐怖心から、心身のバランスを崩しやすくなります。
そこでSNSを活用して、ネット上でのつながりを広げておくことが重要になるでしょう。
昨今はスマホを活用するシニアも増えており、より一層シニアのSNS活用が広がっていくはずです。
「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。
 お問い合わせ
お問い合わせ