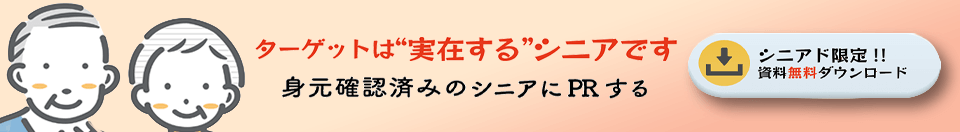1960年代に起きた出来事は?現在のシニアに与えた影響も紹介
「1960年代って何があったんだっけ?」「生まれる前のことだからわからないなあ……」
このように思ったことはないでしょうか?
現在社会の第一線で活躍しているほとんどの人にとって、1960年代とは遠い昔でしょう。
しかし、シニアにとっては若者や子どもだった時代です。
1960年代に起きた出来事は、現在のシニアの行動や価値観に大きく影響していると考えられます。本記事では、1960年代の出来事についてまとめた上で、特に現在のシニアに大きな影響を及ぼしたことについて詳しく解説しています。ぜひ記事を最後までご覧ください。
目次
1.現在のシニアは1960年代を若者や子どもとして過ごしている
1960年代という時代は、現在シニアと呼ばれている世代(本記事では概ね65歳以上とします)の人たちの多くが、若者か子どもだった時代です。
2025年現在85歳の人は、1960年代半ばの1965年には25歳でした。現在75歳の人は15歳、現在65歳の人は5歳でした。
人間は、20歳頃までに体験した文化を懐かしむとされています。
参考:「なつかしさ」はビタースイート。記憶心理学者とたどるメカニズムと心理的効果 | OTEMON VIEW
その文化を懐かしむ気持ちから消費行動が生まれることも知られており、「ノスタルジー消費」と呼ばれています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
シニア世代の大半は、1960年代という時代を、20歳になるまでに過ごしています。この時代の文化や出来事が、現在のシニアの思考や行動に与えている影響は大きいと考えられるのです。
なお、シニア世代や若者世代といった分類は、世代の分類の一種ではありますが、さらに細かい分類もあります。詳しくはこちらの記事で解説しておりますので、参考にしてください。
2.1960年代に起きた出来事
1960年代に起きた代表的な出来事を年表形式で紹介します。
| 年(西暦) | 出来事 |
| 1960 | ・日米新安全保障条約が結ばれる・安保闘争激化・カラーテレビの本放送開始・「国民所得倍増計画」が打ち出される |
| 1961 | ・四日市ぜんそくが発生・NHK連続テレビ小説が放送開始・国民皆保険・皆年金制度が施行開始・ソビエト連邦(現:ロシア他)が初の有人宇宙飛行・東ドイツが東西ベルリンの境界を封鎖(ベルリンの壁を建設) |
| 1962 | ・首都高速道路が芝浦~京橋間で初の開通・YS-11(戦後初の国産旅客機)初飛行・キューバ危機が起きる |
| 1963 | ・日本初のテレビアニメ『鉄腕アトム』が放送開始・NHK大河ドラマが放送開始・三井三池三川炭鉱炭塵爆発と鉄道事故の鶴見事故が同日(11月9日)に発生・ケネディ米国大統領暗殺される |
| 1964 | ・東海道新幹線開通・東京オリンピック開催・日本人の海外観光渡航自由化 |
| 1965 | ・朝永振一郎が日本人で2人目のノーベル賞(ノーベル物理学賞)を受賞・いざなぎ景気(好景気)が始まる・ベトナム戦争の始まり |
| 1966 | ・日本の総人口が1億人突破・ビートルズ来日・中国で文化大革命が始まる |
| 1967 | ・第三次中東戦争勃発 |
| 1968 | ・「少年ジャンプ」が創刊される・川端康成が日本人で3人目のノーベル賞(ノーベル文学賞)受賞・3億円強奪事件が発生する・大学紛争激化 |
| 1969 | ・東大安田講堂事件・東名高速道路が全通・アポロ11号が月面着陸 |
大前提として、1960年代という時代は、日本の実質経済成長率が年平均10%前後だった、高度経済成長と呼ばれる時代です。経済成長に伴い、国民の生産・消費活動が活発になっていきました。そして、経済活動を支えるために高速道路や新幹線といった交通インフラが整備されていったのです。
また、アジア初のオリンピックである東京オリンピックが1964年に開催されたことは、1960年代の出来事として欠かせないのではないでしょうか。
その一方で、四日市ぜんそくの発生に代表されるように、公害が深刻になっていったのもこの時代です。
そのほか、NHKの連続テレビ小説や大河ドラマ、テレビアニメの放送開始、漫画雑誌の『少年ジャンプ』の創刊など、現在も続いているコンテンツが1960年代に始まったことも特徴的です。
ここからは、シニアに大きな影響を与えたと考えられる出来事に関して、個別に詳説していきます。
高度経済成長
1955年頃から1973年頃までの時代は、日本の高度経済成長期と呼ばれています。1960年代の10年間は、丸ごと高度経済成長期に入っていて、国民の暮らしが豊かになっていった時期でした。
1960年に、当時の池田隼人内閣は、1961年4月からの10年間で、国民総生産を2倍以上に引き上げる「所得倍増計画」を発表します。計画に基づき、インフラの整備や、産業の高度化、生産性向上や科学技術振興、そして失業や賃金格差への対処、福祉の推進といった施策が行われます。国民総生産は実際に、1964年には倍増したのです。
1960年代は、多くのシニアにとって懐かしさを覚える時代であり、そして暮らしがどんどん良くなっていった時代でした。1960年代を「あの頃はよかったなあ」と思い起こすシニアが少なくないことは、想像に難くないでしょう。
1960年前後の人々の暮らしがリアルに再現されているとして評価が高い『ALWAYS 続・三丁目の夕日』という映画があります。『ALWAYS 三丁目の夕日』という映画の続編であるこの映画は、昭和30年代の東京の下町が舞台で、シニアにとっては、自身の青春時代を思い起こさせるような作品です。当時を知らない人にとっても、当時の価値観や生活スタイルを知ることで、シニア向け事業のマーケティングに関する示唆が得られる映画といえます。
そして『ALWAYS 三丁目の夕日’64』は、タイトル通り1964年の東京が舞台である続編です。東京オリンピックの開催を目前に控え、ビルや首都高速道路などの建設が進んでいる東京の様子が描かれています。
なお、景気のよかった1960年代とは打って変わって、1970年代には日本はオイルショックといった経済危機を経験します。
1980年代後半には再び空前の好景気を迎えましたが、1990年代前半のバブル崩壊以来、日本は長引く不況を経験しました。
シニアが若い時期を過ごした1960年代が、シニアの行動に与える影響が大きいことは否定できませんが、シニアも景気のよい時代ばかりを生きてきたわけではないのです。
また、高度経済成長は、格差を生むきっかけとなった一面もあります。高度経済成長は、日本の主力産業を第一次産業から第二次、第三次産業へと移していきました。産業の転換は農村から都市部への人口の移転につながります。結果として都市圏へ移動し就職・教育の機会を得て所得の向上という恩恵を受けた層と、地方にとどまり続けた層の間に、収入・消費・社会的な経験等の格差が発生したのです。
学生運動
1960年代は「学生運動」が活発な時代でもありました。学生運動とは、主に大学生による社会的・政治的な運動を指します。1949年頃までに生まれた、いわゆる団塊以上の世代は、1960年代に大学生として過ごした世代です。実際に学生運動に参加した人も多かったでしょう。
1959年から1960年にかけては「60年安保(あんぽ)闘争」が起きました。
1951年に日本とアメリカ合衆国との間で締結された、日米安全保障条約を改定することに対し、反対する人々が起こした大規模デモ運動でした。
このデモに多くの大学生が参加したのです。
特に1960年6月15日には、デモ隊が国会議事堂構内になだれ込み、警官隊と激しく衝突します。この衝突でデモ隊の学生1人が死亡したほか、双方の重軽傷者は数百人にのぼりました。
安保条約の改定はなされたものの、当時の岸信介内閣は、社会の混乱の責任をとる形で総辞職を余儀なくされたのです。それほど激しい闘争でした。
1968年には「大学紛争」が激化し、数多くの大学で学生運動が起きます。紛争の直接の要因は、学費の値上げや、学生の管理体制への不満など、大学によってさまざまでした。しかし背景には、ベトナム戦争に対する反戦や、1960年に改定された日米安保条約の自動更新の阻止などの、政府に対して反発する気運があったとされています。
東京大学の安田講堂を学生が占拠し、1969年1月18日から19日にかけて、機動隊による封鎖解除が行われた「東大安田講堂事件」は、大学紛争中の事件の中でも特に有名です。
1949年頃までに生まれた世代は、以上で述べたような学生運動を、自分で体験した世代です。その一方で、1950年以降に生まれた世代の、学生運動に対する受け止め方は異なっています。
団塊以上の世代の民衆は、学生運動を含めたデモ活動を通じて、政府と戦おうとしました。しかし、それで社会が大きく変わることはなかったのです。1950年から1965年頃に生まれた世代(2025年に60歳から75歳になる世代)は、社会が変わらないという現実を目の当たりにしました。結果として、次第に無気力かつ無関心な考え方を持つようになり「しらけ世代」と呼ばれるようになったと言われています。
しらけ世代については、下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
国民皆保険・皆年金制度の導入
1961年に、国民全員が健康保険に加入する「皆保険制度」と、年金制度に加入する「皆年金制度」が実現しました。
現在にも通じる制度の成立です。
国民全員が年金制度に加入できたことによって当時の人々が得られた、老後の暮らしへの安心感は、世代によって大きく異なることはなかったと考えられます。しかし、人々が実際に老後を迎えてみると、必ずしも期待通りの結果にはならなかったのです。
戦前生まれの世代は、年金の支払いの負担が少なく、年金を受け取る際は、給付が手厚かったため年金制度の恩恵を大きく受けました。
しかし、1950年〜1955年頃以降に生まれた世代は、年金だけでは十分な収入が得られなくなり、逃げきれなかった世代と言われています。そのため、老後の生活設計の見直しを余儀なくされているのです。
少し昔の分析ですが、厚生労働省が2015年に発表した『平成26年財政検証結果レポート —「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」(詳細版)—』の中で、生年ごとの年金保険料負担総額に対する年金給付総額の倍率(支払った保険料の何倍の年金が受給できるのか)が試算されています。
1945年生まれの厚生年金受給世帯の倍率は5.1倍にも及んでいます。しかし、1950年生まれだと4.1倍に急落し、1955年生まれは3.4倍にまで低下しているのです。1945年生まれと1955年生まれの間には、相当な格差があると認めざるを得ません。ひとくちに「シニア」といっても、そのシニアの中で、受け取っている年金の手厚さが異なっているのです。国民皆年金制度は1960年代の出来事でありつつ、1961年当時子どもや若者だった世代と、上の世代の老後の生活に、大きな格差を生んでしまった制度ということになります。
参考:平成26年財政検証結果レポート(406ページ) 厚生労働省
こうした点からも、マーケティングの観点では、65歳以上の人を「シニア」の言葉でひとくくりにできないのです。
3.シニアが経験した出来事から読み取れることは?
シニアの中でも1940年頃以降に生まれた世代は、高度経済成長期を子どもや若者として過ごしてきました。景気の悪い時代しか経験していない若い世代と比べて、お金を使うことに対してある程度楽観的になっていると考えられます。
また、テレビアニメや『少年ジャンプ』がスタートして、いわゆるオタク文化が花開き始めたのも1960年代といえます。収入の多くをオタク系の趣味につぎ込むシニアも、少なくはないでしょう。
ただし、シニアに以上のような消費行動の特徴があるとしても、すべてのシニアにあてはまるわけではありません。高度経済成長によって所得が向上したのは主に都市部で就職をした層であり、所得向上の恩恵にあずかれなかった層との間には格差が生まれました。また、1950年頃以降に生まれた世代は、上の世代と比べて、1960年度に施行された年金制度で割を食っているという実態もあります。
経済的にゆとりのないシニアに対しては、経済力のあるシニアと同じマーケティング戦略は通用しないでしょう。
例えば旅行をしようと働きかけたり、趣味や娯楽への出費を促したりしても、効果は薄いはずです。むしろ、就業のあっせんといった形で収入の少なさを補う手助けをするとか、支出を減らすために生活のダウンサイジングを促すといったアプローチの方が好まれるでしょう。
シニアといっても、その経済力やライフスタイルはさまざまです。それぞれの層の特徴を把握して、適切なマーケティング戦略を立てていくことが重要です。
4.まとめ
1960年代の出来事が現在のシニアに与えた影響は大きいと考えられますが、シニアの中でも、世代やライフスタイルによって、出来事から受けた影響は異なります。
老後の暮らしぶりも、1950年頃に生まれた世代を境に大きく異なっています。
マーケティングにあたっては、「シニア」をひとくくりにするのではなく、シニアの中にも世代や経済力などが異なるさまざまな消費者層が存在することを認識した上で、マーケティング戦略を立てる必要があるのです。
シニアのリアルな感情や行動原理を知るのに適した媒体の1つがSNSです。
シニアSNS「おしるこ」は、会員資格が50歳以上に限定されているので、世代を絞ってインサイトを知ったり、広告を出したりするのに適しています。広告の詳細は以下よりダウンロードしていただけますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
シニア市場の相談を簡単予約
課題やお悩みをお聞かせください。専門スタッフが最適な戦略を提案します。